
退屈だなぁ
ポール・マッカートニーの「アナザ・
ディ」という歌に、「It’s just another
day.」という歌詞があるんですけど、
「今日もまた昨日と同じ日だ。あぁ、つ
まらない」というような歌なんです。
確かに今日は昨日と同じ日だと思ってい
たら、その日にどんな新しいことが起こ
っても、当人はその新しさには気づきま
せん。
どんな新しいご縁があって、どんな未知
の世界に抜け出す扉が開いていたとして
も。
まぁ、40才までに子ども2人、子どもは
私立の学校に入れて、家のローンを払っ
て・・・という風に決めてかかっていた
ら、その日程に関係ない情報が入ってき
ても情報としては取り入れません。
何しろ、関係ないんだから。
大半の人は、無駄な回り道をせずに最短
キョリでゴールに向かおうとします。
それがフツー。
何たってワレワレ、何も起こらないよう
に日々気をつけているんですから。


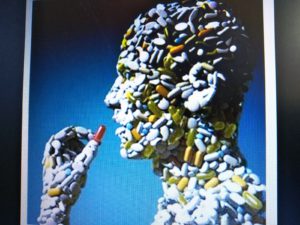
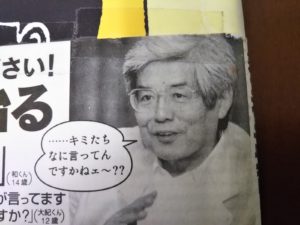
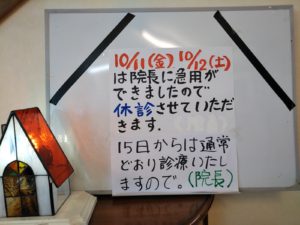
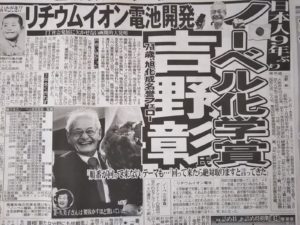


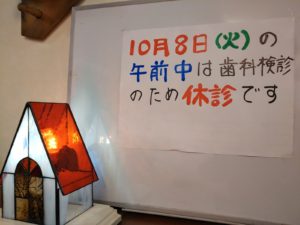

最近のコメント