
海賊
明るい所から急に暗い所に入ると、最初
は何も見えないのに、徐々にモノが見え
るようになります。
30分くらいもかかる。
逆に、暗い所から急に明るい所に出ると
最初はまぶしくてモノが見えづらいので
すが、徐々にフツーに見えるようになる。
約5分くらいです。
視覚細胞には、わずかな光でも捉えられ
るため、主に暗い場所の視力を生み出す
桿体細胞と、明るい場所で色や形を認識
できる錐体細胞というのがあって、明る
い所→暗い所は錐体細胞か桿体細胞にゆ
っくり切り替わるので、時間がかかる。
どうやらそれを、暗順応と言うらしい。
逆に暗い所→明るい所では、桿体から
錐体に早く切り替わるので、5分でOK。
それを明順応と言うらしい。
そういう話を知って、ワタクシ、アニメ
や映画で出てくるあの海賊が決まって
片目に眼帯しているのは、暗順応を維持
するのが目的なのか?と思いました。
(今までは、かわいそうに片目を切られ
たんだなと思っていた)
つまり、海の上で明るい甲板から暗い船
倉に入った時、眼帯をずらすだけで中の
様子がわかるのだ。
明るい場所で作業している最中に突然
戦闘が始まっても、暗順応が生きている
片目を使えれば困ることはない。
もしこれが真実なら、目の特性を生かし
た、海賊のスーパースペシャルテクニッ
クだ。
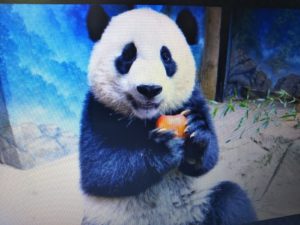
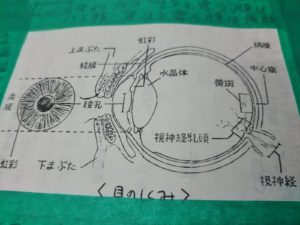
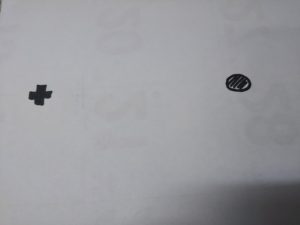
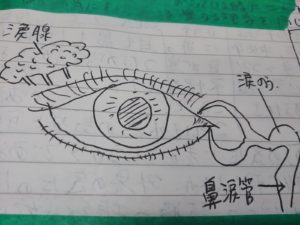
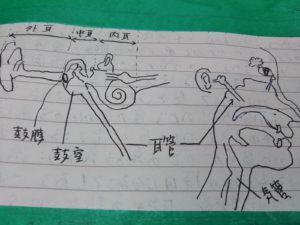
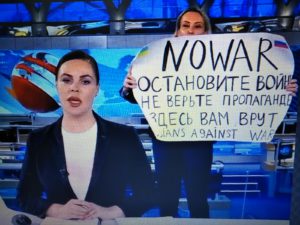
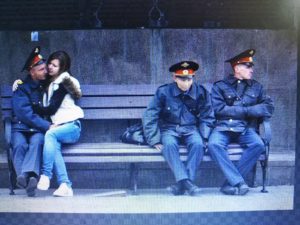

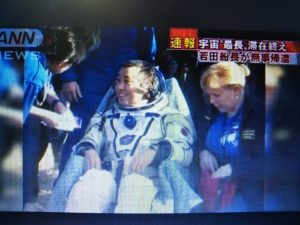
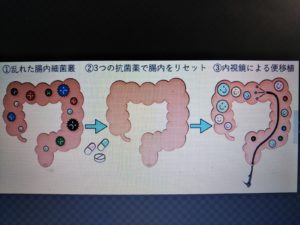

最近のコメント