
世界の金融界に影響を与えるヨーロッパのロスチャイルド家先日の地震・北海道大停電で、「あと1時間で水が止まる」という自衛隊筋の情報が出回りました。
実は”デマ”でした。
ワタクシも、情報源を確認せずに、水を汲みました。
情報と言えば、19世紀のロスチャイルド家が巨万の富を得ることができた話が有名です。
1815年に、ナポレオン率いるフランス軍とイギリス・オランダ・プロセインの連合軍による「ワーテルローの戦い」が始まりました。
この時、イギリスは、国債を発行して戦費を調達。
だから、この戦争でイギリスが負ければ、英国国債は暴落します。
勝てば、暴騰。
ある朝、証券取引所に、ロスチャイルドが青ざめた顔してやってきました。
彼はすでに金融界では大物。
ロスチャイルドは突然、英国債を大量に売却し始めたのです。
その場にいた人たちは皆、イギリスが戦争に負けたと勝手に判断。
終日、イギリス国債の売りが殺到し、大暴落。
しかしこの後、ロスチャイルドは、他の代理店を使って、こっそり、暴落したイギリスの国債を買いあさっていたのです。
この時、市場の6割のイギリス国債をロスチャイルド家が買い占めたといます。
翌日、「イギリスが戦争に勝利した」という情報が入ると、イギリス国債は大暴騰。
ヨーロッパ中に優れた情報網を所有していたロスチャイルド家は、事前に連合軍の勝利を知っていたのデス。
一度暴落させてから買い占めて、巨万の富を得ることができたというワケ。
ロスチャイルド家が他のプレーヤーよりも情報網、資金力、そしてマーケットでの影響力を持っていたからこそ、実現できたのデシタ。

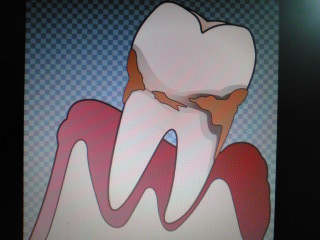
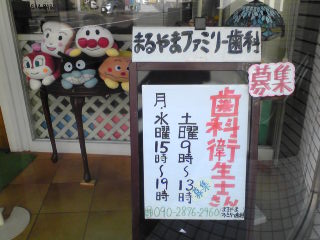



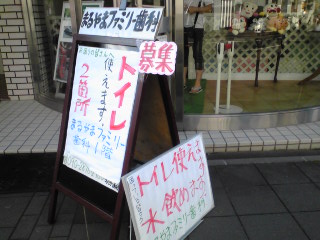


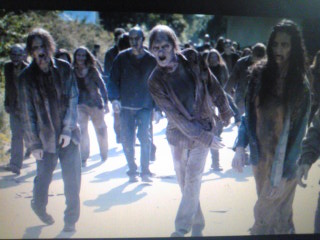

最近のコメント