
部屋をのぞきこむカラス(イメージ)ワタクシごとで恐縮なのですが、先日は半年前に亡くなった妻の父の6回目の月命日でした。
今回は、うちの奥さんと母さんと、親戚のおばさんの3人でお参り。
いつものように坊さんがお経をあげて帰ったあと、3人で談話していると、突然ベランダに一羽のカラスがやってきた。
低い階層にはカラスはよく来ますが、ここはふだん滅多に来ない11階。
「珍しいねぇ」と母。
しかも、そのカラス、3人が話している内容を聞いているかのように、ずっと、こっちを見てる。
誰も、「しっ、しっ、あっちへ行け!」なんて言いませんそのうち、うちの奥さん、ピンときて、「あのカラス、亡くなったお父さんじゃないか?」皆さん、顔を見合わせて、「きっと、そだね」「みんな、元気そうだな。今日もみんなで集まってくれのか?アリガトな」きっと父がカラスの姿を借りてみんなに会いにきてくれたのでしょう。

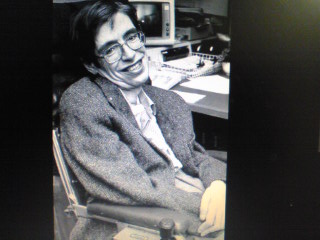

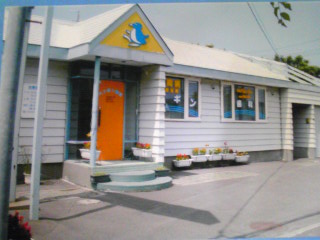



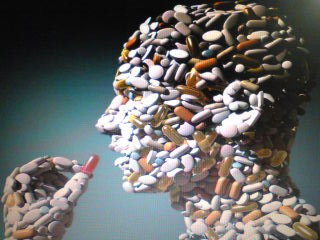


最近のコメント