
保育園の先生たちに導かれて、りーぶる保育園の子ども達がやって来ました。
先日は近所のりーぶる保育園の歯科検診
でした。りーぶる保育園はもう7~8年前
からご縁があります。りーぶる保育園は
まるやまファミリー歯科の徒歩圏内なの
で散歩がてらに来てくれます。

子供たちのお世話をするうちのスタッフ(左側にいるS藤さんとK沢さん)
誰かが言ってたんだけど,まるやまファミ
リー歯科の前の道が散歩コースになって
いるらしい。

まるやまファミリー歯科の前の道は保育園の散歩コースになっています。子供たちはアンパンマンのぬいぐるみに挨拶してくれるんですよ。
その日は朝から待合室がにぎやかでした
。その日はクリスマス前の歯科検診とい
うこともあって、待合室はクリスマス仕
様でした。

検診は一人10秒以内でパッと口の中を診
る。長く口を開けていると、いろいろあ
るんですよ。上手にお口を開けてくれた
子にはアンパンンのシールを選んでもら
います。もちろん上手に出来なかっに子
にも選んでもらいますよ。


アンパンマンシールが次々と子供たちのものになりました。
そしてもう一つ、おもちゃの宝箱も用意
してあります。せっかく歩いて来てくれ
たのですから、ただで帰すわけには参り
ません。宝箱の中身を選んでもらう。そ
して診療室をアンパンマン仕様にしてお
くと、0~3才児の子ども達は喜ぶんで
すよ。

おもちゃの宝箱もどんどん無くなりました。
もちろんB.G.M.はクリスマスシーズンだ
けど、アンパンマンの歌です。0~3才児
はクリスマスよりもアンパンマン。アン
パンマンの生みの親、やなせたかしさん
には感謝・感謝です。

『アンパンマン』の生みの親、やなせたかし氏
ワタクシ思うのですが、ひょっとして、
『アンパンマン』って、『お母さん』の
ことではないでしょうか?赤ちゃんが泣
けば、ミルクや母乳を与える。母乳は血
液だから、顔の一部ならぬカラダの一部
です。

『アンパンマン』って、『お母さん』?
さらに子供が泣けば、スグに飛んで行き
、昼であろうが夜であろうがスグ起きて
、布団をかけなおす。お母さんは子供を
守る為に、昼夜関係なく、助ける準備が
出来ているのです。

子供が泣けば、スグに布団を掛け直します。
アンパンマンも言っています。『困った
ことがあったら、いつでも呼んでね!』
ってね。赤ちゃんはまだ言葉が完成して
いないので、困ったことがあれば、泣い
てお母さんを呼ぶんですよ。お母さんは
飛んで来る。ほら、まるでアンパンマン
みたいでしょ。こんなマネ、到底父親に
は出来ませんよ。グーグーよ~寝ておる
。スミマセン、また話が脱線してしまい
ました。

バイバイ
おしまい。



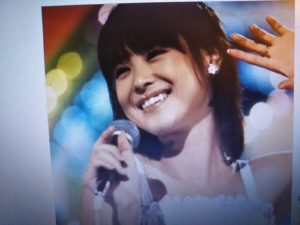
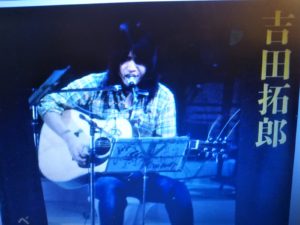
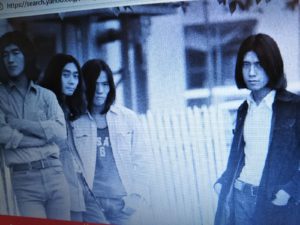


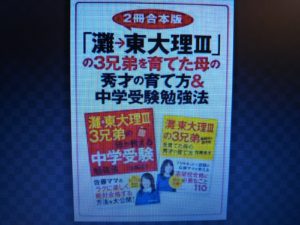




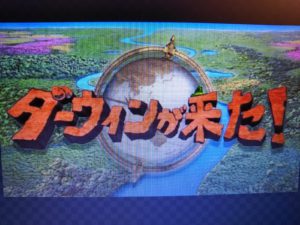

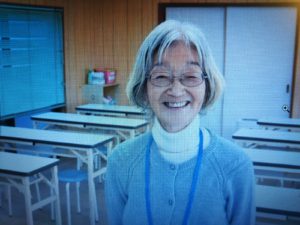


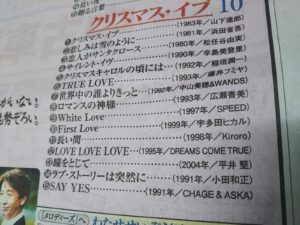

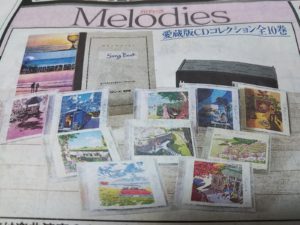

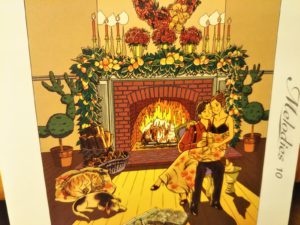
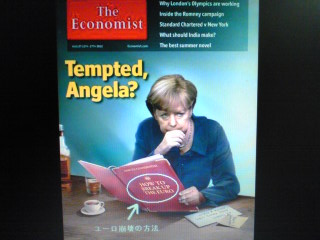
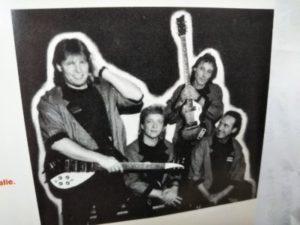
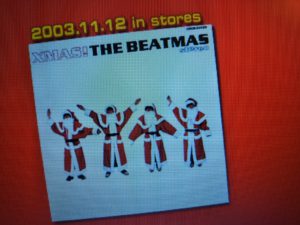

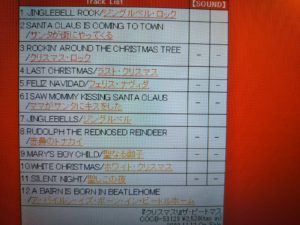
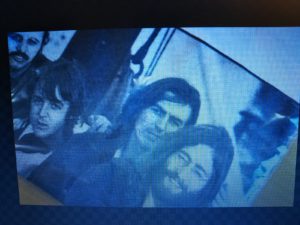
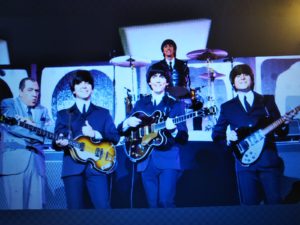
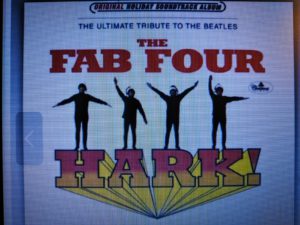


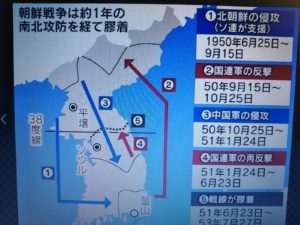

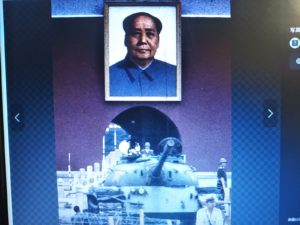
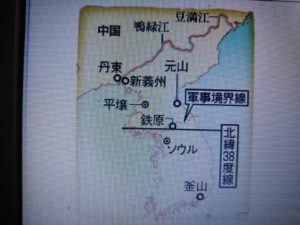
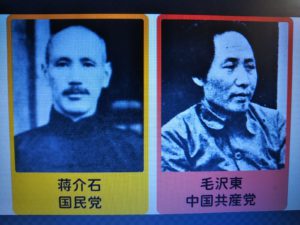







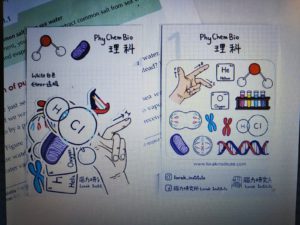



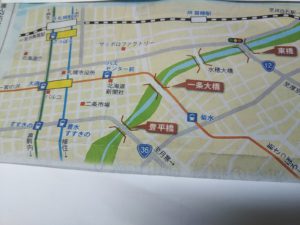

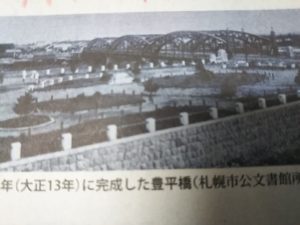
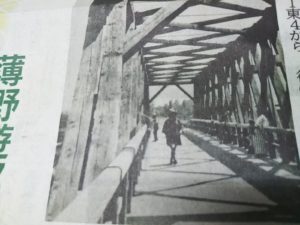

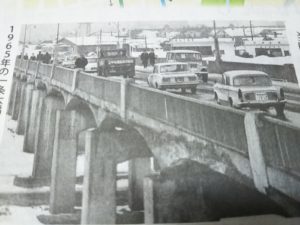


最近のコメント