
最新情報
素朴なギモン「ハトはどうしてみな同じ向きにとまっているの?」


マリリン・モンロー
空を見上げると、電線によくハトがとまって
います。
よく見れば、みんな同じ向き。
今まで特に何も考えていなかったのですが、
先日、Eテレのピタゴラスイッチを見ていた
時、「ハトはどうしてみな同じ向きにとまって
いるの?」という歌がありました。
それによりますと、どうやら風の向きが関係
しているそうで、自分に向かって風の吹いて
くる方向に頭を向けるのです。
順方向です。
これが逆なら、羽根の中に風が入ってきて
羽根がバサバサになって、寒くて寒くてのん
びりとまっているわけには参りません。
昔ハリウッド映画でマリリン・モンローが
地上を歩いていた時、地下鉄の排気口から
突然風が起こってモンローのスカートが
舞い上がったシーンがありましたが、風向き
を間違えたらハトもあんな感じです。
「まえがき」「あとがき」を読んでみた。


「まえがき」 「あとがき」
本屋さんでブラブラしていたら、ある本が
目に留まりました。
教育学者の斉藤孝著『10分あれば書店に
行きなさい』という本。
そこにこんなことが書いてありました。
***********
「まえがき」では、たいていその本の趣旨
が熱く語られている。肩に力が入っている
場合も多いから、なかなか読み応えがある。
「あとがき」には著者の個人的な感想や
身辺雑記的なことがやや気楽に書かれてい
ることが多い。一見すると「おまけ」。
「おまけ」だからない場合もアル。
***********
まぁ、著者が持てるエネルギー全てを注ぎ
込んだような本もあれば、残念ながらそれ
ほどでもない本もあるワケで、著者が全身
全霊を注いだ本なら本文を書き終わった後も
興奮していて、その“余熱”で何か書きたく
なる。
たぶんアレ、映画のDVDによくついている
「メイキング」のようなものじゃないかな。
手の内をさらしたくなるアレ。
で、いろんな本の「あとがき」を読んで
みた。
確かに人柄がよくにじみ出ていると思い
ました。
強気で自画自賛する人もいれば、遠慮がちに
感謝とも謝意ともつかない言葉を並べている
ヒトも。
まぁ、人それぞれ。
わざわざ「ハワイの別荘にて」とか、「マン
ハッタンの夜景を眺めながら」など書いて
締める人もイル。
温かい読者なら、1冊を書き上げた労に免じ
てこれくらいの自慢は〇〇してあげてネ。
礼儀正しくすることは、「生き延びるためのいちばんいい知恵」
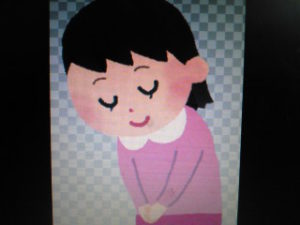
礼儀正しくするといいことばかり
まるやまファミリー歯科では、フッ素塗布を
しています。
就学前のチビッコたちは、フッ素塗布をして
もらったら、一目散に待合室に向かおうと
します。
するとお母さんに呼び止められ、「ホラ、
先生にちゃんと”ありがとうございました”と
言うんだよ。」と注意を促されます。
母親は子どもに「礼儀正しくすること」を
教えているのです。
これは、言うなれば、生き延びるための知恵。
子どもがまず「礼儀正しく」ということを
教え込まれるのは、子どもからすると世の
中のほとんどの人間が権力を持っている人間。
子どもであるというのは、まわりのほとんど
全ての人間によって傷つけられる可能性が
あるということ。
それくらい、「子どもである」というのは
リスキーな状況。
母親は、「あなたはすごく無力なのだから、
まずきっちりディフェンスを固めておきな
さい」という思いを伝えているのです。
なんたって、初めて会った人から最大限の
情報と支援を引き出すために一番有効な
方法は、「礼儀正しく友好的な口調で語り
かけること」ですから。
それに、スキを狙う輩たちは、礼儀正しく
されるとそれ以上入ってゆけない。
まぁ、ドラキュラが嫌がる十字架みたいな
もんです。
子どもがピッチャーで、親がキャッチャー。

ワタクシ、週末は運動不足を解消する
ために、近くの小学校の体育館で仲間と
テニスをしています。
雪のまだ積もらない頃、校庭ではよく
小さな男の子とお父さんがキャッチボー
ルをしているのを見かけます。
男の子はまだボールの投げ方を覚え始め
たばかり。
ボールがあっちに飛んだり、こっちに行っ
たり。
それを見てて、「親子の関係はキャッチ
ボールだ」という話を思い出しました。
もちろん、子どもがピッチャーで親が
キャッチャー。
優れたキャッチャーは、ピッチャーの持ち
味を理解し、それを引き出す。
毎回全力投球させるのではもたないので、
うまく緩急を織り交ぜる。
ピッチャーの身に何か異変があればすぐに
気づき、声をかける。
時々ピッチャーが暴投しても、身を挺して
受け止める。
そして何より、そこにいるだけでピッチャ
ーに安心感を与えることができる。
親と子の関係はこうでなくちゃという話。
何ともまぁ、ホントに見習いたいものデス。
口の中の天井、鼻の下の床。

ワレワレ歯医者は治療する時、口の中の
天井が必ず見えます。
だいたい皆さん、天井を持っている。
この天井を口蓋というのですが、実はコレ、
同時に鼻腔の床でもあるんです。
この天井が抜けると、モノが鼻の中に入っ
てしまう。
生まれつきそういう状態が生じることが
あって、それを口蓋裂というのですが、
こうした先天異常は実は大変なことをイミ
しています。
それは、口の天井が抜けるという状態は
ホ乳類以前はあたり前だったということ。
口蓋裂は、言ってみれば一種の先祖返り。
この天井が抜けるといろいろ具合の悪い
ことが起こります。
子どもがお乳を吸おうとすると鼻から
空気が入ってしまうのでうまくお乳が吸え
ないし、逆も起こる。
口に吸い込んだお乳も鼻に抜けてしまう。
ホ乳類はお乳を吸って大きくなるので、
この天井ができました。
お乳を吸わない魚や両生類、ハ虫類はこの
天井はいらないのです。
でもなぜかハ虫類のワニでは例外的に天井
がアル。
ワタクシ、子供の頃、家でニワトリを
飼っていました。
ニワトリが水を飲むのを見ていたら、口に
水を含んだ様子で頭を上げる。
おそらくああいう飲み方でないと、水が
鼻に入ってしまうのでしょう。
天井がないですから。
まぁ、この天井がなければ、お口のトラブ
ルがあった時、耳鼻咽喉科に行こうか歯医
者に行こうか迷ってしまう。
鼻の穴から管を入れたらその先には歯とか
ベロとかあったということになっちまう。
チンパンジーは3才で頭の成長が止まる。

まるやまファミリー歯科では、乳幼児に
フッ素塗布しています。
小学校へあがる前の5才くらいの子って、
ずいぶん成長したなぁと思います。
ところで、頭の発達についてこういう話が
あります。
自分の子どもが生まれた時に、同じ頃生ま
れたチンパンジーの子を探してきて、兄弟
みたいに一緒に育てたアメリカ人の研究者
がいます。
ヒトとチンパンジーの発育を比較したので
すが、生後3才まではどうみてもチンパン
ジーの方が上だった。
運動能力は高いし、何をするにしても気が
きいている。
ところが3才を過ぎて4~5才になってく
ると、ヒトの方はどんどん発育が進むので
すが、チンパンジーは停滞してしまう。
身体はもちろん発育するんだけど、頭が
ダメ。
その頃にヒトとチンパンジーを分ける何か
が現れるようなのデス。
3歳児は自己中心的。
5歳児は相手の立場に立てる。
チンパンジーは3才で頭の成長が止まって
しまうので、自己中のまま。
サル山でボス支配になるのは、たぶん自己
中で成長が止まるからで、相手の立場を考
えなければ必ずケンカになる。
そうなれば強い方が勝つに決まっています。
転勤して行く人、来る人。

まるやまファミリー歯科付近には、転勤族の
方が多く住んでいらっしゃいます。
3月に入ってくると、まるやまファミリー
歯科の患者さんも「来月から転勤なんです
よ。いろいろお世話になりました。」とか、
「急に転勤が決まっちゃって・・・」など
いろんな話が耳に入ってきます。
そんな時、「札幌暮らしはいかがでしたか?
ブラッシングはココとココを気をつけて、
転勤先でも時々は歯石を取ってもらってネ」
と言って送り出します。
その瞬間、いろんな思いが頭をよぎります。
寂しいものです。
4月になれば転勤族の新しい患者さんが
来られます。
そして、その時から新しい関係が始まる。
まぁ、その繰り返し。
札幌に来られたからには、是非いい思い出を
持ち帰っていただきたいものです。
吸血鬼の歯


吸血鬼「ドラキュラ」 ドラキュラの歯
4本の前歯の隣が犬歯です。
吸血鬼になると、これが突然伸び出します。
これが伸びないと、あまりすごみがあり
ません。
マントを着たただの顔色の悪い人に見える。
だから吸血鬼は犬歯が伸びるのでしょう。
吸血鬼のギセイ者は、ふつう首に歯の跡が
2つついています。
これは犬歯の跡。
咬まれた人は吸血鬼になる。
犬歯から何かが体内に入ったことになる。
ヘビの毒牙でも、確かに毒腺の分泌物が歯を
経由して注入されます。
ヘビの毒腺は歯から生じた腺なので、歯の
中に開いています。
ところで、サルの仲間とヒトの仲間の違い
は、犬歯が伸びるか伸びないか。
サルは伸びる。
こう考えてみたら、犬歯が伸びる吸血鬼
って、先祖の方向に向かっていることに
なります。
進化の方向に逆行しているので、将来発展
の余地はあまりないと思う。
「ロミオとジュリエット」はたった5日間だけのお話

映画「ロミオとジュリエット」
歯医者さんで平凡な日々を送っていると、
「アッ」という間に1週間が経ってしまい
ます。
「あっ」という間に過ぎてしまうと言えば、
ラブ・ストーリーの代名詞ともいえるシェー
クスピアの名作「ロミオとジュリエット」。
運命の2人が出会って悲劇的な結末を迎え
るまで、たった5日間でした。
<1日目>出会い
<2日目>結婚、ロミオがジュリエットの
従兄弟を殺す
<3日目>ロミオはジュリエットの元を去る
ジュリエットは結婚を迫られる
<4日目>ジュリエット自殺を装う
<5日目>2人とも自殺
でも、もっともっと有名な事件で、もっと
もっと短いものがあります。
それが、1600年に起きた天下分け目の
関が原の戦い。
朝、戦いが起きて、その日の昼前には決着が
ついていた。
戦ったのはたった3~4時間だけ。
ボーッとしてテレビを眺めていたら、3~4
時間なんて「あっ」という間です。
濃い時間と薄い時間があるんだなぁと思う。
最近のコメント