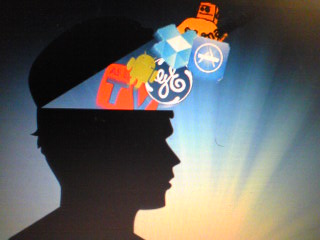
ヒトの背丈や体重は、いくら個人差があるといっても、まぁせいぜい2倍かそこら。
でも仕事の成功なら、何百倍、何千倍の個人差が出てしまう。
ところで脳の話ですが、右脳は左脳の10万倍の能力があると言われています。
ビル・ゲイツや孫さんのような大成功した経営者のユニークな発想が右脳から生み出されたとしたら、確かに右脳の能力は左の10万倍あるのかなぁと思う。
ウチの国では、小学校の頃から読み・書き・そろばんなんかの左脳の訓練が中心。
右脳の活動がどうしても抑えられてしまう。
よく歯のコンクールで、小3までの子はとてもイイ絵を描くんだけど、小4あたりからまともな絵であったり、どこかで見たことのあるなぁという絵を描くようになります。
俗に言う、学校で誉められるような絵。
だいたい、右脳ってのは扱っているハンイが左脳とは比べようのないほど広くて、人類が積み上げてきた何百万年の生物の歴史がおさまっていますからねぇ。
あのモーツアルトが34年かそこらの生涯の中で曲を700も800も作れたのは、アレ、右脳の中から貯まっていたのを勝手に引っ張り出してきたんじゃないかと思う。




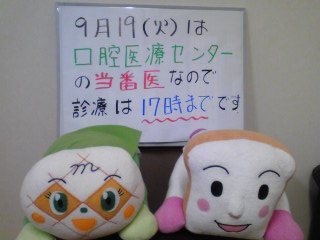

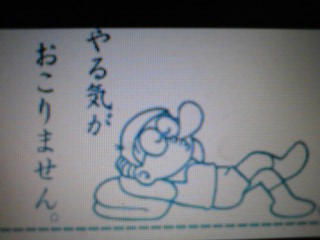
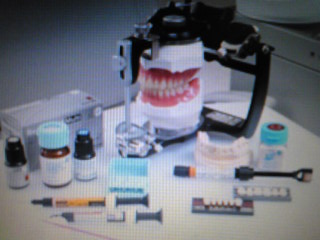
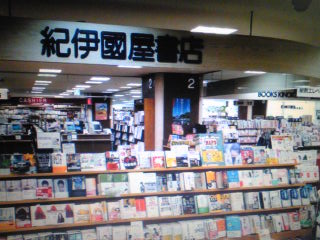
最近のコメント