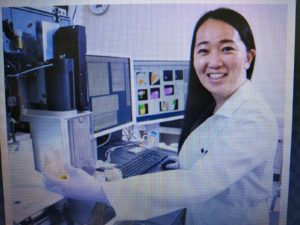
イギリスの科学雑誌『ネイチャー』に載って忙しくなった茂呂さん
【続きです】
茂呂さんたちが、この細胞を見つけるま
では、自然免疫というのはマクロファー
ジとか樹状細胞という大きな免疫細胞が
食べるというお仕事をするのが、自然免
疫だと言う風に思われていました。でも
、『ILC2』は食べない細胞だった。
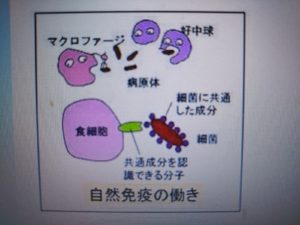
それまで、自然免疫は食べる細胞だと考えられていましたが、茂呂さんの見つけた自然免疫『ILC2』は食べない細胞だった。
従来の認識は『自然免疫は食べるのが仕
事』。新たな認識は『自然免疫にも指令
を出す系統がいる』。アレルギーの世界
では獲得免疫が主役で自然免疫はワキ役
だと考えられて来ました。
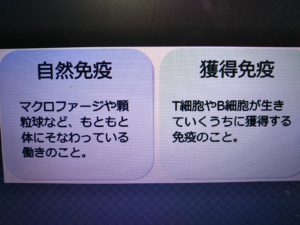
アレルギーと言う病気自体が杉や食べ物
にしろ、間違って認識するのは獲得免疫
だけなので、自然免疫というものは抗原
(アレルギーの原因)を間違って認識でき
ないので、あんまり関係ないだろうと考
えられて来ました。自然免疫も主役の1
つであったということです。
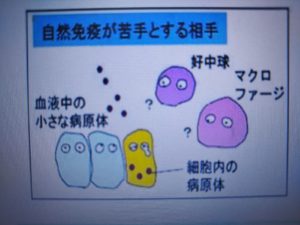
寄生虫がいる時に『ILC2』がドンドン
活性化してくれて、粘液を出すってこと
は、寄生虫を排除するためにはとてもい
い事ですが、これがですね、同じメカニ
ズムが花粉のようなアレルゲン(原因物
質)が入って来た時も、粘液を増やすこと
が起きていたんですよ。

寄生虫の代わりに花粉が入って来ても自然免疫『ILC2』は寄生虫と勘違いして、せっせと粘液を増やすんですよ。
まさに『ILC2』はカラダの粘液に侵入し
てきたものが、寄生虫でなく、花粉の場
合も、その刺激によって危険シグナル
『IL‐33』が放出されると自動的に活性化
。寄生虫侵入と同じ状況を作ってしまい
花粉を追い出すために、せっせと粘液を
増やす。これがアレルギー反応となって
現れるのだ。

寄生虫の代わりに花粉が来ても、『寄生虫が来やがった!』と勘違いして、寄生虫を体外に追い出すために、せっせと粘液を増やすんですよ。
相手が何か明確にわかってないのに危険
信号を受け取っちゃいますからね。まあ
、それが自然免疫のおバカさんなところ
です。

『寄生虫か何か知らないけど、何かが来たので何とかしなくちゃ!』と思って、粘液を増して体外に追い出す。
『ILC2』というう細胞は『I‐L33』が出
てくると、『あっ、何かしなくちゃ!』と
いうことで、鼻水とか咳とか痰とかが出
て来る。まあ、清潔な環境に少なくとも
免疫はついって行ってない。

免疫は清潔な環境には少なくともついって行ってない。
有名な論文だと、牧場で牛とか馬とか草
原もあって、そういう所で育った子とい
うのはアレルギー疾患の発症率が物凄く
低いってのはどの国でも言われているこ
とです。

牧場や不衛生な環境で育った子供たちはどこの国でもアレルギーの発生率がもの凄く低いんです。
まあ、アレルギーになりにくい体質って
のは、子供の時にきちんとかかるべき病
気にかかったトカ、そういうことなんで
すよ。

子供時代にきちんとかかるべき病気にかかった子はアレルギー疾患になりにくいんですよ。
おしまい